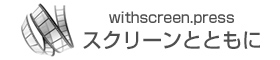「わたくしどもは。」富名哲也監督
地域に根差した映画というと、観光名所や名産品がばんばん登場するか、地元の人たちがいっぱい出演する素朴な味わいのものといった印象が強い。それはそれで決して悪くはないし、面白いものもあればつまらないのもあって1作1作で評価すべきなのだが、そんなパターンとまるっきり異なる地域映画と出くわすと、何ともうれしくなる。
昨2023年の東京国際映画祭コンペティション部門に選出された「わたくしどもは。」は、新潟県の佐渡島を舞台に、生と死、自然と産業、過去と現世といったさまざまな側面を滋味あふれる映像美と確かな演技力でつづった他に類を見ない作品だ。手がけたのは、現在は新潟県を拠点に創作活動をしている富名哲也監督で、これが長編2作目に当たる。前作の初長編「ブルー・ウインド・ブローズ」(2018年)も佐渡で撮影していて、その撮影後に訪れた佐渡金山にインスピレーションを受けて金山をメイン舞台に映画を撮ったと、9月に開かれた東京国際映画祭のラインアップ発表会見で富名監督は語っていた。
「小さな作品で、クルーも少なく、撮影期間も短かったのですが、この機会でワールドプレミアムとしてみんなに見てもらえるのは光栄に思います」と話していたが、残念ながら映画祭では見ることができず、ようやく公開前のマスコミ試写で目にすることができた。
映画は、正直に言ってかなり難解だ。ある殺風景なコンクリートの施設で、一人の女(小松菜奈)が目を覚ます。自分が何者で、どこから来たのかもわからない彼女は、この施設で清掃員をしているキイ(大竹しのぶ)に助けられ、アカやクロと名乗る少女と暮らす部屋に連れていかれる。ミドリと名付けられた彼女はキイと同じ清掃員の仕事に就くが、猫に導かれた部屋でやはり過去を失くした男(松田龍平)と出会う。ミドリは男をアオと名付けるが……。
といったストーリーを書き連ねてもあまり意味はない。どうやらミドリとアオは過去につながりがあった男女で、会うべくして再び会い、そして恐らくずっと一緒にいられるわけではない。ここでほんのわずかな時間を共有し、この後はどこへ行くのかは登場人物の誰も何も語ってくれはしない。ただ緑濃い佐渡の自然と、山頂がいびつな形にえぐられた金山の跡と、真っ暗闇の坑道が、横幅の狭いスタンダードサイズのスクリーンを静かに彩るだけだ。
ぼんやりと見つめながらふと頭をよぎったのは、ポルトガルの異才、ペドロ・コスタ監督の作品だ。移民や労働者たちの心象風景をポルトガルの歴史とともに織り上げるコスタ映画は、ゆったりとした動きと訥々としたせりふで深い感銘をもたらすが、「わたくしどもは。」もちょっと似たような感覚に陥った。
だがコスタ作品がいわゆるプロの俳優ではない人たちのほとんど素のままの姿を捉えているのに対して、こちらは主立った登場人物はみな芸達者な俳優が演じている。主役の小松菜奈、松田龍平に加えて、大竹しのぶ、片岡千之助、石橋静河、田中泯といった表現力に定評のある出演者たちが、押しなべて表情をあまり変えることなく、いかにもせりふらしいせりふを語る。言ってみれば動きのある朗読劇みたいな印象で、これらの言葉の数々が佐渡金山の風景に溶け込んでこの世ともあの世ともつかぬ世界を見事に表出する。なるほどこの味わいは、コスタ監督のように素人を起用しては作り出せるものではないだろう。
そんな深みのあるお芝居を支えるようなカメラワークがまた渋い。カメラを横に移動させるパンよりもズームインとズームアウトを多用して、実際の目線ではなく心の目で見つめるよう観客をいざなう。それもわざとらしくなくごくごく繊細な動きで、ミドリとアオの世界観を微妙に表現する。
音声も秀逸で、虫の声や小川のせせらぎ、木々の葉擦れに至るまで微かに響いてきて、そこにほんの少しだけ野田洋次郎が手がける落ち着いた音楽がかぶさると、佐渡の淡い光が実に柔らかく回り出す。背景と一体化してかなりのロングショットで捉えた役者のせりふもくっきりと耳に届くし、音響にも相当に力を込めたことがうかがえた。
富名監督は北海道の出身だが、鹿児島出身の妻で映画プロデューサーの畠中美奈ともども新潟に移り住んで、今後も新潟を舞台にした映画を撮っていくという。次はどんな驚異の地域色を創出してくれるのか、楽しみで仕方がない。(藤井克郎)
2024年5月31日(金)から東京・新宿のシネマカリテなど全国で順次公開。
©2023 テツヤトミナフィルム

富名哲也監督作品「わたくしどもは。」から。佐渡金山で出会ったミドリ(右、小松菜奈)とアオ(松田龍平)は…… ©2023 テツヤトミナフィルム

富名哲也監督作品「わたくしどもは。」から。作品は緑濃い佐渡島のオールロケで撮影された ©2023 テツヤトミナフィルム