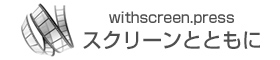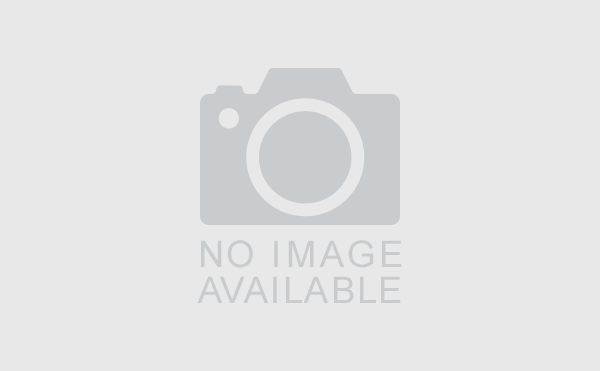第297夜「また逢いましょう」西田宣善監督
京都を拠点に映画の製作、配給などを手がけるオムロの西田宣善社長との出会いは、30年以上前にさかのぼる。当時はオムロピクチャーズと称して東京に事務所を構えていたころで、恐らく同社が宣伝を担当した韓国映画「銀馬将軍は来なかった」(1991年)のチャン・ギルス(張吉秀)監督が、日本公開を控えた1993年10月に来日したときにインタビューをしたのが最初だったかと思う。以来、「屋根裏の散歩者」(1992年)の実相寺昭雄監督や「ローカルニュース」(1999年)の中村義洋監督、函館山ロープウェイ映画祭など、さまざまな取材でお世話になってきた。
近年も「レミングスの夏」(2016年、五藤利弘監督)、「嵐電」(2019年、鈴木卓爾監督)、「信虎」(2021年、金子修介監督、宮下玄覇共同監督)といった話題作をプロデュースするなど活躍の場を広げている。栄枯盛衰の激しいこの業界にあって誠にご同慶の至りだが、今度はよわい60を超えて劇場映画の監督に初挑戦したという。これは何が何でも試写に駆けつけねばならない。
作品は京都でデイケア施設を営む伊藤芳宏の著書「生の希望 死の輝き 人間の在り方をひも解く」を原案に、「夜明けまでバス停で」(2022年、高橋伴明監督)などの脚本家、梶原阿貴が脚色。介護の現状をモチーフに笑いと人情味を織り交ぜながら、あくまでも前向きのエネルギッシュな映画に仕立てている。
東京で漫画家の夢を追い続けている優希(大西礼芳)は、一人暮らしの父、宏司(伊藤洋三郎)が転落事故に遭ったとの知らせを受け、大急ぎで京都の実家に戻る。宏司は命に別状はなかったものの手足に重い麻痺が残り、優希がしばらく実家にとどまって父の面倒を見ることになった。
無口で頑固な父とは会話もほとんど交わさない優希だったが、何かと気にかけてくれるケアマネジャー(カトウシンスケ)の勧めもあり、父に介護施設「ハレルヤ」に通わせることにする。この「ハレルヤ」の武藤所長(田山涼成)がハイデガー哲学を施設運営に活用するなどユニークな人物で、恐らく原案者の伊藤がモデルなのだろう。「救いの共同体を作りたい」という理想に基づく理論を優希たちに熱く語りながら、通所者の心も体も元気にしていくという過程がほのぼのとしてすがすがしい。
中でも「死は誰にも平等に訪れる」という重くなりがちなテーマを、数々のユニークなレクリエーションや通所者の個性的な人柄を巧みに組み合わせてからっと明るく描いているのが光る。認知症や突然死などは、当事者の家族や施設の介護職員にとって非常に重くつらいもののはずだが、決して軽々しくもなく、でもあくまでも誰もが迎える自然な営みとして活写する。武藤所長を演じる田山をはじめ、ベテラン職員役の中島ひろ子や利用者役の梅沢昌代の存在感に加え、田中要次、筒井真理子といった芸達者がちらっとの登場ながらいい味を出していて、見ていて安心感がある。一方で介護職員の待遇改善など社会的な課題にもきちんと触れており、全国で奮闘している関係者への敬意や支援の思いも感じられて、実に爽快な気分にさせられた。
中でも、あ、これぞ映画だな、とうれしくなったのは、ラストの大西礼芳と中島ひろ子のはじけっぷりだ。これまで「花と雨」(2020年、土屋貴史監督)や「夜明けまでバス停で」(2022年、高橋伴明監督)など、印象的ながらもどちらかというと地味な役が多い気がする大西と、「櫻の園」(1990年、中原俊監督)で主役を飾った後、今ではすっかり脇役に徹している感のある中島が、ここまでエネルギーを爆発させるのは意外性がある。いかにも映画らしい解放感があり、さすがは作品のプロデュースだけでなく、数々の名匠、巨匠の研究書、評論集など数々の書籍の編集にも携わってきている西田監督だけのことはあるなと感じ入った次第だ。(藤井克郎)
2025年7月18日(金)から京都のアップリンク京都、大阪のシネ・ヌーヴォ、19日(土)から東京の新宿K’s cinemaなど全国で順次公開。
©Julia /Omuro

西田宣善監督「また逢いましょう」から。父親の介護をすることになった優希(大西礼芳)は…… ©Julia /Omuro

西田宣善監督「また逢いましょう」から。優希(左から2人目、大西礼芳)は介護士の向田(左、中島ひろ子)の協力で、父、宏司(伊藤洋三郎)のリハビリに取り組む ©Julia /Omuro