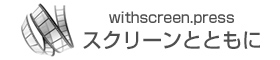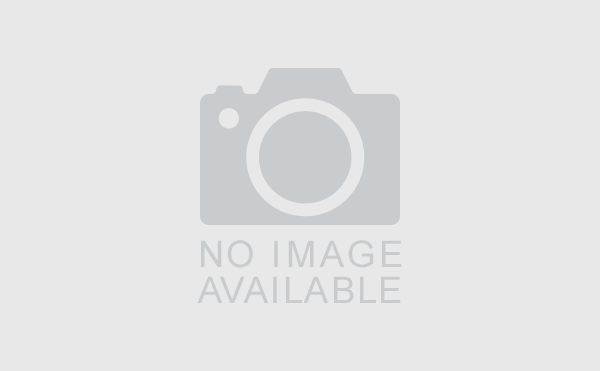第301夜「わたしは異邦人」エミネ・ユルドゥルム監督
トルコと言うと忘れられないテレビ番組がある。おヒョイさんこと藤村俊二がイスタンブールの街を走り回って、それでいて観光の見どころ紹介になっているというドラマともバラエティーともつかぬ紀行番組で、子ども心にものすごく面白かった記憶がある。調べてみたら、恐らく1972年に日本テレビ系列で放送されていた「スーパースター・8☆逃げろ!」の1本ではないかと思うのだが、どうやら7回だけの放送で打ち切りになったらしい。
その他の回でどこを取り上げていたのかは全く覚えていないのだが、なぜかイスタンブールだけは強烈に印象に残っていて、憧れの都市ナンバーワンだった。何しろ西洋風と東洋風が混在したような街並みで、こんなエキゾチックな景観が世界にはあるんだと、小学生だった身には新鮮な驚きがあった。以来、機会があったらぜひとも訪れてみたいと思いながら、一度も果たせぬまま今日に至っている。
「わたしは異邦人」は、そのイスタンブールで孤児として育った女性が、自分を生み捨てた母を探して地中海に面した都市、シデを訪ねるという映画だ。イスタンブールは出てこないし、シデという町のことはこれまで全く知らなかったが、スクリーンに映し出される風景に思わず息を呑んだ。まるでギリシャのような古代遺跡が立ち並んでいて、砂浜が広がる海岸線の向こうに黄金色の夕日が沈む。トルコだけでなくギリシャも行ったことはないけれど、イスタンブールとはまた違ったトルコの知られざる景観に目が釘付けになった。
映画は、主人公の女性、ダフネ(エズキ・チェリキ)がバスでシデに到着したところから始まる。バスに居残っているフセインという若い男性(バルシュ・ギョネネン)と別れて下車したダフネは、ぶつくさ文句を垂れるおやじがいるホテルに宿を取り、どこかの遺跡で撮影されたと思しき母の不鮮明な写真を頼りに、その居所を探し求める。
娼婦のナジフェ(セレン・ウチェル)に声をかけると、逆に彼女の娘との仲介役を頼まれる。こうして2人でナジフェの娘に会うのだが、うん? 3人のやりとりが何か不自然だなと思ったら……。いやいや、ここはこの映画最大の驚きの場面で、皆まで言うまい。ただバスで別れたはずのフセインは頻繁に顔を見せるし、ホテルの文句垂れのおやじやら、古代ギリシャの巫女やら、登場人物の素性が徐々に明らかになってくるエンターテインメント性を帯びた展開にわくわくが止まらない。あ、今度はそう来たか、と、これが初の長編となるエミネ・ユルドゥルム監督の巧みな作劇にすっかり魅了された。
作品のざっくりとしたテーマを言えば生と死であり、洋の東西が交わるこの地は生者と死者も交錯するということなのだろう。どこか日本的な幽玄の美も醸しつつ、ギリシャ風の古代遺跡群がヨーロッパの香りを漂わせる。中でも死者の魂が黄泉の国に渡るのに、三途の川ならぬ遠浅の海に入っていくという表現がじんわりと心に染み込んできて、人間の感受性や死生観といったものは世界中どこもそんなに違いはないんだなと妙に納得した。
この作品は昨2024年の東京国際映画祭「アジアの未来」部門に出品され、横浜聡子監督ら3人の審査員によって最高賞に当たる作品賞に選ばれている。映画祭では作品を見る機会を逸したが、授賞式後の記者会見でうれしそうに質疑に応じるユルドゥルム監督の姿に接することができた。
「トルコは家父長制の強い国で、映画業界も男性中心の社会だが、少しずつ女性監督の活躍は増えている」と今後の期待を口にしたユルドゥルム監督は、一方で「トルコは古い文明を引き継いでいる地で、アナトリアという地域は4000年の歴史を誇ります。そこでは多種多様な民族が入り交じり、しかも人間性にあふれた文明があった。ヒッタイト文明、ギリシャ文明、ローマ文明といろんな歴史を受け継いでいるからこそ今日の社会があるのであり、そのことに敬意を払いたいという思いをこの映画に込めました」と話していた。
この作品でこんなにも豊かで親しみのある文化があることを知った以上、イスタンブールと合わせてますますトルコを旅したくなった。(藤井克郎)
2025年8月23日(土)から東京・渋谷のユーロスペースで公開。

エミネ・ユルドゥルム監督のトルコ映画「わたしは異邦人」から。母親の居所を探して、ダフネ(右、エズキ・チェリキ)は古代都市のシデにたどり着く

エミネ・ユルドゥルム監督のトルコ映画「わたしは異邦人」から。地中海に日が沈むころ、魂たちは……