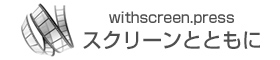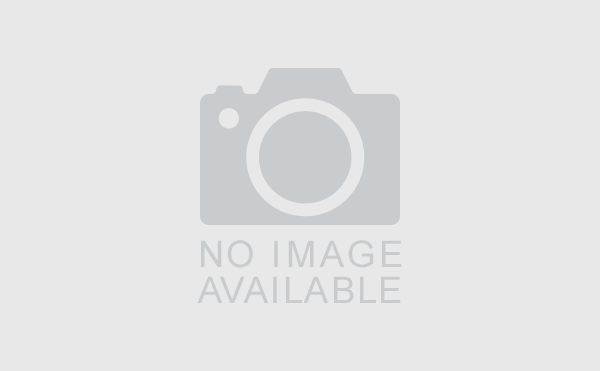第288夜「ただ、愛を選ぶこと」シルエ・エヴェンスモ・ヤコブセン監督
北欧ノルウェーの森に生きるある家族に密着したドキュメンタリーなんだけど、その暮らしぶりはなかなか先進的というか、時代のかなり先を行っている。ペイン家は、長女ロンニャ、次女フレイヤ、長男ファルク、次男ウルヴの4人の子どもを豊かな自然の中で育てようと、物質主義に染まった街を脱出してここに移り住んできた。就学年齢になっても学校には通わず、ホームスクーリングで両親から教育を受け、食べるものはほぼ自給自足で、家畜の牛も自分たちで解体する。稼ぎ頭は写真家として活躍する母親のマリアで、イギリス出身の父親ニックと農作業を分担しながら充実した毎日を過ごしている。
マリア自らが家族の姿を捉えた動画もふんだんに使われているし、自然とともに生きる地球に優しい暮らしのヒントになるような映画なのかな、と思いきや、始まってものの10分もたたないくらいで意外な方向に進んでいく。何と、主人公と思われた母親のマリアががんでこの世を去ってしまうのだ。主役が途中で入れ代わる作品はそんなに珍しくないかもしれないが、冒頭すぐにいなくなるとは予想だにしなかった。
「ただ、愛を選ぶこと」というこの映画の真骨頂はここからだ。ペイン家の4人の子どもたちのうち、マリアの連れ子だった長女のロンニャは実の父親と住むことを選んで家を出る。ニックは残された3人の子どもと何とか以前のような生活を続けようと試みるものの、一人で農場を運営することは極めて難しい。一家はやむなく街の近くに移住するが、果たして喪失に打ちひしがれた家族に再生の希望は見えるのか。
といったペイン家の劇的な変貌を、カメラは克明かつ冷徹に写し取る。中でも最も影響を受けたのは、思春期を迎える次女のフレイヤだろう。母親を亡くした悲しみも癒えないうちに、彼女は学校という全く新しい環境に身を置くことになる。マリアの理想は、子どもたちを大自然の中で家畜や野菜を育てながら、何の束縛も受けずに伸び伸びと成長させることだった。学校生活で社会性を身に付けるよりも、規則に縛られない自然の中での学習こそ子どもたちには必要だと感じていた。
だがそんなマリアの願いに反して、フレイヤはありきたりの学校に通うようになる。最初は慣れない人付き合いに戸惑いを見せたものの、やがて積極的に声をかけてくる級友と交じり合ううち、徐々に豊かな感受性が芽生えていく。その一方で、ゲームやテレビなどそれまで無縁だった人工的な娯楽にもどんどんと毒されていく様子が、情け容赦なく映し出される。
もう10年も前からマリアのブログに魅了され、マリアが2019年に他界した直後からカメラを通してペイン家を見つめ続けてきたシルエ・エヴェンスモ・ヤコブセン監督は、決してどちらの生き方がいいかを提示することはしない。ただ一家の日常と一人一人の偽らざる思いをすくい取るだけで、教育とは、家族とは、そして人間らしく生きるとは、をさりげなく問いかける。しかも映り込んでいる風景はまるでカメラなど介在しないかのような自然体で、それだけヤコブセン監督自身がこの家族に溶け込んでいることがうかがえる。長い時間をかけてじっくりと寄り添ったからこその真実が画面の端々から浮かび上がってきて、何とも濃厚なひとときをスクリーンの前で体感することができた。
映画を見終わった後、1992年に取材で小笠原諸島を訪れたときの記憶がよみがえった。かつて小笠原は地上波の電波が届かず、一切のテレビ放送が映らなかったが、1989年から1991年にかけてNHK、日本衛星放送(現WOWOW)が相次いで衛星放送の本放送を開始して、テレビの視聴が可能になった。住民の生活の変化を連載記事に仕立てるための取材だったが、父島の小学校でとても興味深い話を耳にする。伊豆諸島最南端の青ヶ島に地上波の電波が来たとき、それまで存在しなかったいじめが子どもたちの間で起きたのだという。テレビが映るようになって小笠原にもいじめが出るかもしれない、と本土出身の先生は懸念していた。情報過多の文明社会と情報が隔絶された大自然と、どちらの環境が子どもにとっては幸せか。なんてことも、ちらっと脳裏をよぎった。(藤井克郎)
2025年4月25日(金)、東京・シネスイッチ銀座など全国で順次公開。
© A5 Film AS 2024

シルエ・エヴェンスモ・ヤコブセン監督のノルウェー映画「ただ、愛を選ぶこと」から © A5 Film AS 2024

シルエ・エヴェンスモ・ヤコブセン監督のノルウェー映画「ただ、愛を選ぶこと」から © A5 Film AS 2024