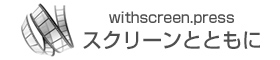女性映画の視点と使命
第38回東京国際映画祭が2025年11月5日に閉幕した。世界中から集まった多様な映画と触れ合うせっかくの機会だったが、今回は多忙にかまけてわずか4作品の視聴にとどまった。来日映画人との交流、取材も、事前申し込みなど制約が多く、ごく限られた参加だったが、そんな中で感じたことを振り返ってみたい。(藤井克郎)
☆よりよい社会のために映画ができること
見ることができた4本の映画のうち3本は、エシカル・フィルム賞にノミネートされた作品だった。この賞は2023年の第36回から登場したセクションで、映画祭にエントリーされた全ての新作の中から「人や社会、環境を思いやる考え方、行動」という「エシカル」の理念に合致する優れた3作品をノミネートし、審査委員会で1作品を選出するとなっている。
この「エシカル」の理念というのが、今一つよく分からない。2回目の実施だった昨年は、ベルリン国際映画祭で最高賞の金熊賞を獲得しているベナン、セネガル、フランス合作「ダホメ」(マティ・ディオップ監督)が受賞しており、フランスに略奪されたダホメ王国の美術品の返還運動を取り上げた力強い社会派作品だった。今も根強く残る植民地主義への告発という点でエシカルなのかなとも思ったが、その前年の第1回は性自認に悩む児童の揺れる思いと家族とのつながりを描いたスペイン映画「ミツバチと私」(エスティバリス・ウレソラ・ソラグレン監督)と、全くタイプの異なる作品が選ばれている。
昨年、授賞式とそれに続くトークセッションに出席したとき、エシカルの理念について質問したところ、映画祭のプログラミング・ディレクターを務める市山尚三さんは「よりよい社会を作るにはどうするかを考えるという理念のことで、そのテーマに沿う作品はたくさんあるが、その中でも特にお勧めの3本を選んだ」と回答。さらに審査委員長だった俳優で映画監督の斎藤工さんは「自分以外の他者の個性を理解して、時として寄り添うという思いやりみたいなものを、エシカルと捉えている」と答えてくれた。
昨年はノミネート3作品のうち1本を見逃していたので、今年は3本とも鑑賞して、そこからエシカルの理念を探ってみたいと考えた。今年のノミネートは、西アフリカで兵士として生き延びる幼い少年が主人公のフランスのアニメーション作品「アラーの神にもいわれはない」(ザヴェン・ナジャール監督)と、ベルギーを舞台にセックスワーカーの世界に足を踏み入れるシングルマザーを描いたベルギー、フランス合作の「キカ」(アレックス・プキン監督)、そして認知症の祖母の介護をしながら貧民街で精いっぱい生きる若者の物語、ブラジル映画の「カザ・ブランカ」(ルシアーノ・ヴィジガル監督)の3本だったが、昨年の「ダホメ」ほどの覚醒は得られなかったかなというのが正直なところだ。
特に「キカ」は、なぜこの主人公が性産業に加担しようとするのかが不鮮明で、作品の完成度としてどうなのかという気がした。シングルマザーが生きづらいのも、歪んだ性嗜好の男性が多いのも、全て社会のせいというわけでもないだろうし、ちょっと焦点がぼやけた感は否めない。ほかの2本も、貧困や差別が少年兵やヤングケアラーを生み出すというのはそうかもしれないとは思うものの、これまでもさまざまに描き出されてきたモチーフではある。ただ「アラーの神にもいわれはない」のアニメーションという手法は、なかなか意欲的な試みだなと感じた。
今回、審査委員長を務めたのは俳優で映画監督も務める池田エライザさんで、学生応援団の3人とともに選び出した受賞作は「カザ・ブランカ」だった。結果はともかく、なぜこの3本をノミネートしたのかに興味があり、昨年に続いて授賞式とトークセッションに出席しようと取材を申し込んでいたのだが、前日の11月3日午後6時過ぎ、「取材登録が上限を超えたため、お席をご用意できませんでした」とのメールが来た。後日、その模様を収めた動画を事務局に送ってもらったが、フォトセッションを見ると取材のカメラは7人しかいないようだ。それほど力を入れていない部門かもしれないが、もう少し取材の枠を増やしてもいいのではないのかな、というのは出席できなかった者のひがみか。
☆男性的秩序と女性的混沌のバランス
昨年から始まったウィメンズ・エンパワーメント部門についても言及したい。女性の活躍支援を目的に、「女性への視座」を持った作品の上映とトークイベントなどから構成されており、今年はカナダ、エジプト、スペイン、日本などの7本の映画と3つのイベントが用意されていた。
映画の上映はコンペティション形式ではなく、世界の女性映画の今を紹介するという意味合いが強いが、今年は残念ながら1本も見ることはかなわなかった。その代わり、と言っては何だが、ハー・ゲイズと題したトークと、ラウンドテーブルの「女性映画祭の力」という、いずれも11月3日に東京ミッドタウン日比谷のBASE Qで開かれたイベントに参加した。やっぱり取材できるかどうかは前日の夕方まで分からなかったが、無事に「ご取材いただけますので、当日会場にてお待ちしております」とのメールが届いた。
ハー・ゲイズは「女性の作り手を招き、その仕事や考え方、一人ひとりの眼差し-GAZE-を学び、共有するトークイベント」とのことで、今年の黒澤明賞に選ばれた中国出身のクロエ・ジャオ監督がゲストとして登壇。途中からは「ふつうの子ども」などの呉美保監督も加わって、熱いトークが繰り広げられた。
2時間にわたって行われたトークの詳細を伝えることは避けるが、興味深いエピソードが飛び出した中でも特に印象的だったのは、月経に関するジャオ監督の見解だ。「このトークが始まる直前に生理が来た」というジャオ監督は、月経中はとてもクリエイティブになってパワーを感じることができるので、生理は大好きだと打ち明ける。
「種の保存というだけでなく、生理は女性の力であり、知恵でもある。人々が躍起になって生理の話を避けようとするのは、実はそれがものすごくパワフルだから。女性の体はものすごく大きな感情を内包していて、毎月、それを破壊して再生しているから痛みを伴うし、感情の混沌を感じることができる」と話すジャオ監督は、何かを提案されたとき、「Let me think(考えさせて)」の代わりに「Let me bleed(血を流させて)」と言っているとジョークを飛ばす。
ただジャオ監督は性差について強調したいのではなく、男性の中にも女性性はあるし、女性の中にも男性性はあると指摘。「人類の長い歴史の中で女性性の意識は抑圧され、追いやられてきたが、男性性が優位な家父長制は女性だけでなく男性も傷つけている。映画作りにはその両方のバランスが必要で、男性的に構築された意識で秩序を保つ一方、女性的な混沌を包含することでより深くなるのです」とジャオ監督は力説する。
後半にはジャオ監督に質問するという立場で呉監督も参加。「生理が来るのが楽しみという人と出会ったのは初めて」と話す呉監督は「血を流させて」というフレーズが気に入ったようで、「私もスタッフに対して使わせてもらいます」と受けるなど、和やかに、でも極めて深い内容で進行した。
ただ残念だったのは、ジャオ監督の新作「ハムネット」は映画祭のクロージング作品だったため、会場を埋め尽くした誰もまだ見ておらず、トークでもほとんど触れられていなかったことだ。アカデミー賞の作品賞や監督賞に輝いた「ノマドランド」など過去作についての裏話はあったものの、映画祭の一環なのだから、上映と連動すればもっと聴衆との交歓ができたのではないかと惜しまれる。
もう一つのラウンドテーブル「女性映画祭の力」は、台湾の台湾国際女性映画祭、韓国のソウル国際女性映画祭、そして日本のあいち国際女性映画祭の代表者が参加。それぞれの映画祭の歴史と現状が報告されたほか、お互いに連帯して女性映画をますます活性化させようという方向で盛り上がった。
3時間が予定されていたものの、議論百出であっという間に時間が経過し、会場からの質疑応答の時間が取れないほどだったが、最後に司会を務めたこのイベントの企画者、近藤香南子さんが「どうしてもお聞きしたいことがある」と言って、台湾と韓国の代表に投げかけた質問が秀逸だった。同じ東アジアの女性映画祭として連帯していきたいという話が出たが、台湾も韓国も日本が植民地化して抑圧した歴史がある。そのことを女性映画祭同士で乗り越えたいという思いでこういう対話を企画したが、何か思うことはあるかという問いかけだった。
これに対して、台湾国際女性映画祭のプログラマーで映画研究者のジュオ・ティーンウーさんは、台湾の女性映画はもともと植民地時代の愛国婦人会から始まっていると指摘した上で、「女性の視点からは抑圧されている人たちに敏感になることができる。国の違いを越えて、女性映画祭が抑圧や迫害というものに対して積極的な役割を果たさなくてはいけない」と強調。またソウル国際女性映画祭のプログラマー、ソン・シネさんは、この質問をしてくれて感謝していると前置きをしつつ「国対国、加害対被害というよりも、もっと大きな帝国主義、侵略主義という観点で語ることができる。帝国主義について、多くの女性映画人がいろんな側面からアプローチを試みていて、そのことについて話し合うのは大いに意味がある」と述べていた。

ウィメンズ・エンパワーメント・トーク“ハー・ゲイズ”で「会場からの質問に答えるクロエ・ジャオ監督(右)と呉美保監督(中央)。左は企画者の進行役、近藤香南子さん=2025年11月3日、東京都千代田区の東京ミッドタウン日比谷(藤井克郎撮影)
☆人と人とのふれあいが生まれる取材の場
最後に、今年から始まったささやかながら非常に重要なトピックについて触れてみたい。ここ最近の東京国際映画祭では、来日する監督や俳優ら海外ゲストに取材しようと思ったら、個別のインタビュー以外では公式上映の舞台挨拶に参加するしかなかった。公式上映は、大半の作品はプレスパスでは鑑賞することができず、通路で長く待たされて、上映後に劇場に入っていって舞台挨拶を聞いて写真を撮って、というのがお決まりだった。その作品を見ようと思えば、別の日に用意されているP&I(Press & Industry)上映に行くしかない。
だが当方が初めて東京国際映画祭に参加した30年ほど前は、毎日、コンペティション部門の記者会見が開かれていたし、来日ゲストだっていろんな意見、質問が飛び交う会見を楽しみにしている人もいるだろう。世界のカンヌ国際映画祭は2016年に一度しか行ったことがないが、やっぱり毎日、公式上映後に記者会見が開かれ、世界各地から集まった記者たちがめちゃくちゃな英語で活発に質問を繰り出していた。
今回、初めて囲み取材と称してコンペティション部門ゲストに質問できる機会が設けられ、たった1回だったが、11月1日に開かれたベルギー、北マケドニア合作「マザー」のテオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督の取材会に参加した。確かに囲み取材というように会場はパーティションで仕切られた狭い空間で、取材側の参加は映画祭公式記者を含めてわずか7人。大半は公式の質問ばかりで、ほかに3人が投げかけて時間切れとなった。
今回は、この直前に「マザー」のP&I上映を兼ねた公式上映があったので映画を見ていたし、機会があったら挙手しようと臨んだものの、ほかの記者から繰り出された質問はかなり濃いものばかりで、ミテフスカ監督も大いに乗ってしゃべっていた。中でも、この作品のモチーフになっているマザー・テレサに、若いころボランティアで会ったことがあるという記者の感想、質問には監督も大感激。ちょっと涙ぐむ場面も見られ、人と人との出会い、ふれあいが一番の魅力である映画祭の神髄に触れた気がした。
ただし、これももったいないなあと思うのは、「マザー」の場合は囲み取材の直前にP&I上映を兼ねた公式上映が行われたから、当方も映画を見て、その流れで取材に参加することができたものの、スケジュール的に全てがそう都合よく組まれているわけではないという点だ。取材に参加する以上、映画は見ておくべきだと思うし、限られた時間内で鑑賞と取材の日程をやり繰りするのがかなり大変なのは変わりがない。
もっとも、ほんのつまみ食い程度しか参加していない身としては、あんまり偉そうに言うことはできない。来年はもうちょっと映画を見て取材もできたらなと思っているので、事前申し込みで落とされないよう、よろしく頼みます。

「マザー」のテオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督の囲み取材は、こぢんまりとした空間でざっくばらんに行われた=2025年11月1日、東京都千代田区の東京ミッドタウン日比谷(藤井克郎撮影)